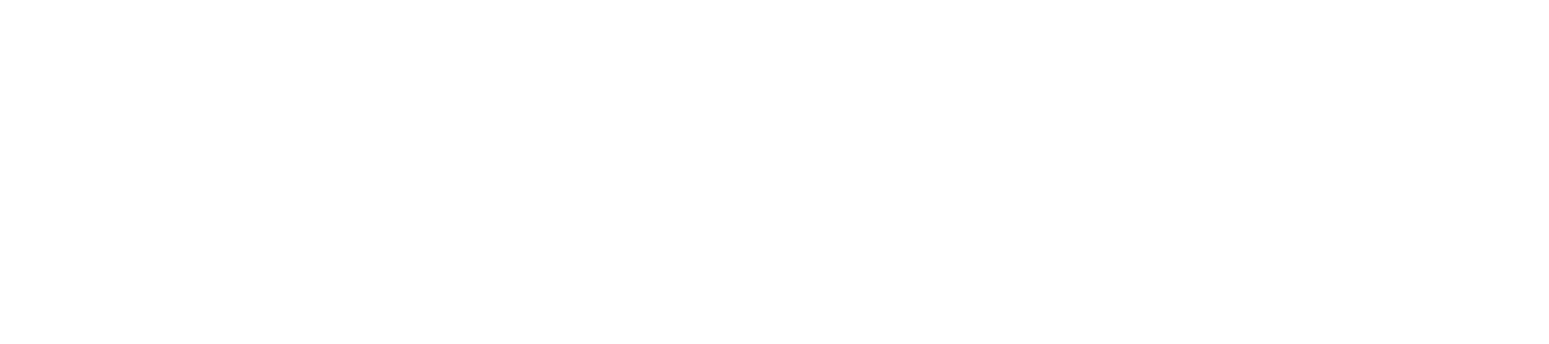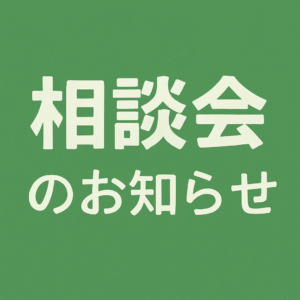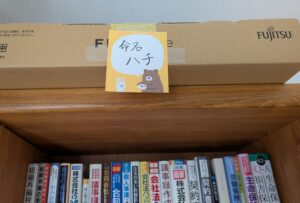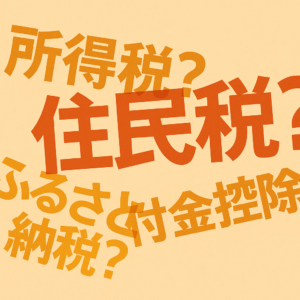神社やお寺に払う色々なお金、考え方を整理してみました。。

商売繁盛祈願!
地元のお寺や神社にちょっとした支払(お賽銭、お守りやお札の代金、お祭の協賛、祈祷料)をすることがあると思います。信仰心から、または地元のお付き合いの一環で支払うお金、ひとつひとつは多額ではないけれど、意外とありますよね。
今回「それって経費に入れていいの?」というご質問があったので、私なりのご回答をまとめておきました。
経費になるのか?
税務上、その支出が経費(法人の場合は損金といいます)になるかどうかは、基本的に「目的」で判断します。そのため、「お寺や神社に払ったお金は経費になる?」に対する回答は、YESでもNOでもなく、「支払った目的によります」となります。
税務上、その支出が経費になるかどうか、判定するための基準は2つ。
・事業上の収入を得るために直接要した費用(原価)か
・業務の管理や維持のために必要な費用か
つまり、売上原価または事業の継続に不可欠な費用と認められる合理的な理由があれば、経費として計上が可能、ということになります。
売上原価になる場合(たまに、あります)
「お寺や神社への支払が売上原価?なにそれ?」というのが一般的な感覚だと思いますが、中にはそんな商売もある、という話。
例えば、とある神社が販売している有名なキャラクターをモチーフにしたお守りを、事業として仕入れて転売したとすると、これは売上原価になります。(転売に関するモラルについては今回の本題ではないので、この際脇に置きます)
また、片付け業を行っている事業者が、お客様から依頼されて仏壇の魂抜きや人形の供養などを行った場合、この支出も、原価として認められる可能性が高いと考えています。
これらの支払は、事業の売上に直結するものであり、当然売価の設定上もこの金額が織り込まれるものだからです。
このような売上原価に関しては、法人でも、個人事業主でも、考え方に大きな違いはありません。ただ、一般的には違和感のある原価であることは事実なので、客観的に価格設定が明らかな先で購入すること、領収書等を必ず保管すること等、後から第三者が見ても事実関係を把握しやすいように心がけておくのが得策です。
管理維持費用→個人事業主は原則、不可
いわゆる「販管費」としての支出、普通はこちらのパターンの方が多いと思います。
この場合、法人と個人事業主で、考え方が異なります。
法人なら、事業の維持に必要であると認められれば経費になります。
個人の場合には、経費にするのが難しいです(過去の裁判で否認されています)。
法人は、純粋に事業を行うために設立された人格であって、経営者個人とは切り離されているのに対して、個人事業主は、ひとりの人格の中に事業主と私人が混在しているということがその理由と言われています。
個人が支出した賽銭、お札、祈祷料などは、基本的に信仰心という「心」から出るものであって、たとえ祈る内容が商売繁盛だとしても、これを私人としての信仰心と切り分けることはむずかしい、というような感覚です。
熊手や神棚、お札など、個人経営の店舗にもよく飾られていますが、厳密に言えばこれは経費にはできない、というのが税務署の公式回答にはなります。
管理維持費用→法人は「目的」による
法人の場合、事業の維持に必要であれば経費になるとすると、「事業の維持に必要である」とは何かという話になります。これは、地域とのつながりを通して事業を円滑に行う、宣伝活動につながる、といった効果が見込まれるかという点を判断の基準にします。
一方で、会社が人格として経営者個人とは切り離されている以上、経営者が特定の宗教を信仰していて、経営者個人としての信仰心から特定の宗教施設に多額の寄付を行う、といったことは、法人としての事業の維持発展には直接の関係がないので、たとえ法人名義でおこなっていたとしても経費性を認められない可能性があります。
では、法人の経費になると判断されるなら、何費で計上するのか?
この場合性質によって、広告宣伝費・消耗品費・交際費・寄付金などを使用します。
広告宣伝費は、そのお金を支払ったことにより、社名や事業内容を広く一般に浸透させる目的で支払う場合に使用します。お祭の提灯、チラシ等に社名を刷り込むなどの費用は広告宣伝費として計上する場合が多いです。
消耗品費は、神棚や熊手など「もの」を手に入れるための代金である場合に使用します。一方で、お札やお守り、玉垣奉納など、確かに名目上の「もの」はあるけれど、それを手に入れることが主目的ではない場合には、寄付金となります。
なお、「御神酒」という検索ワードでこの記事、見られているみたいです。御神酒の場合、祈祷をお願いした際にあくまでも祈祷の一環としていただいたものなのか→主目的は「祈祷」、売店で、「御神酒」を手に入れるために払った金額なのか→主目的は「もの」を手に入れること、という点で判断することになるのかなあ、と思います。
一方奉納品として購入し、神社に渡したお酒は、そもそも自社で使わないので消耗品ではなく、次に述べる交際費か、寄附金になるのかなと。
交際費は、お寺や神社またはその関係者が自社の取引先等で、特定の取引関係の向上のために支出した費用である場合に使用する科目です。
最後の寄付金は少し特殊な経費です。寄付金とは、「何も見返りを求めない支出」です。「喜捨金」と言ったりもします。祈祷料や奉納金は、この扱いになります。
交際費と寄付金については、法人が経費にできる額(損金算入)に一定の上限額があります。交際費は中小法人(資本金1億円以下)の場合800万/年まで、寄付金はその法人の資本金や所得の額に応じて計算した上限額となります。(国税庁タックスアンサー5281)
この手の支払があった場合、税理士的にはまず、金額上限のない広告宣伝費や消耗品費にできないかなあ、という観点で、支払内容を根掘り葉掘り確認しはじめますが、ご協力をお願いします!
領収書(インボイス)がない問題
特に寄付金となる祈祷料、奉納金等の場合、領収書が出ないという問題があります。
この点、法人税法上は、支出したことが事実であれば、大きな問題はありません。
少額の寄付であれば、支出した時点で、お手元の出金伝票に日付や内容を記載して保管しておけば足ります。また相手に渡した金封の写真を保管する等も有効です。
一方多額の寄付で、領収書がもらえない場合には、銀行送金などにするのが望ましいです。現金取引は証拠が残らないので、後から第三者にも確認しやすい方法を採用することで、事実関係を証明しやすくなるからです。
では消費税はどうかというと、消費税はもともと「資産の譲渡、貸付け及び役務の提供」があった場合に発生する税金なので、「もの」を手に入れた場合以外は、その取引自体、そもそも消費税の対象外である場合が多いです。特に寄付金となる性質の支出に関しては、外部で物品を購入して奉納した場合等を除き基本的に消費税は発生せず、領収書にもインボイス番号などの記載はありません。
そのため、お寺や神社への支払について領収書がない場合、取引の根拠を残してあれば、法人税上は経費となる可能性がある(あとは目的次第)、消費税上は、インボイス要件を満たす領収書のある取引でないと難しい、という結論になります。
「なにを」よりも「なんのために」が大事です。
「これって経費になりますか?」のご質問に対しては、必ずまずは「なんのために払ったお金ですか?」と返します。私のお客様はそれぞれ異なる事業を経営されているので、同じことにお金を使ったとしても、その背景や事情はその都度違うからです。
正直なところ、その目的を伺った上でも、判定が白黒はっきりつかないときもあります。法律も現場の通達も、個別具体的な判断を逐一述べるものではなく、基準を示しているにすぎないからです。
そういった場合、私としては、税務上の各種の基準を踏まえた上で、「第三者が客観的に見たら、それは論理が通っているか」という私の感覚を加えてご回答しています。現場ではそれが一番重要な判断軸だからです。(「社会通念上~」という言い方をします)
事業は、地域に支えられながら、時に自分も地域を支えて成り立つものです。
伝統的な祭礼等への協力が事業の発展にも不可欠であることは事実なので、実際のところ過度に多額の支出でなければこの手の話が税務調査等で争点になることは少ないとは感じています。ただ実務上は迷うことも多いので、ご参考になればと思います。
おわりに
ブログの画像に使ったのは、横須賀の叶神社(西)の狛犬の子。
後にも先にも、こんなにお茶目な狛犬を見たことがないです。本来の狛犬はちゃんと台座にいるんですが、その仔犬が脱走して石柱の陰からこっちを見ているんです!
心を奪われる可愛さなので、横須賀にお越しの際はぜひ寄ってみて下さい!