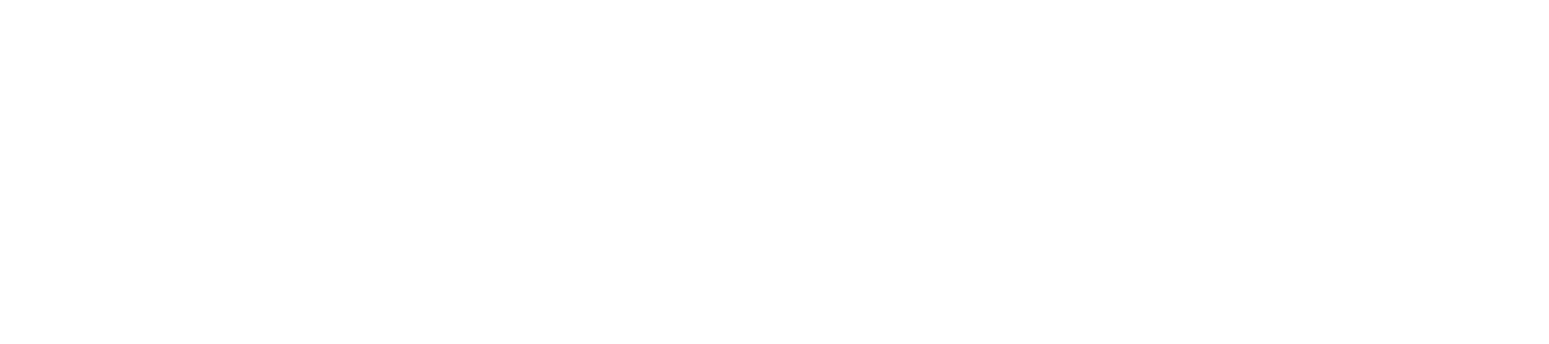▶ご逝去(=相続発生)・ご葬儀
死亡届と死亡診断書については各種手続上重要な書類となりますので大切にご保管をお願いいたします。
ここからしばらくは故人に関する多種多様な書類を管理する必要がある時期になります。相続人の皆様で各種手続書類の管理方法・管理場所について決めておくと後の手続がスムーズです。
▶直後 ~
ご家族がご逝去されたことによりご自身が相続人となることが判明した場合、できるだけ早くご連絡をいただければと思います。
準確定申告・相続放棄・限定承認等、ご逝去後3~4か月内に手続を完了する必要のある手続があるためです。
但し相続人が複数いる場合、相続税の申告は相続人の連名で行いますので、基本的には相続人全員が同じ税理士に依頼されることが望ましいです。
葬儀費用・火葬料・ご逝去前後の医療費等、故人に関する費用の請求書等は、相続税額の計算上課税対象額から控除されますので、ご保管をいただけますようお願いいたします。
合わせて、ご逝去の前後に相続人の方が故人の口座から引き出した預金等がある場合、後日の相続人間トラブル防止・税務調査への反証のため、入出金額と用途を記録しておくことをお勧めいたします。
また、故人が事業経営者であり、かつ許認可が必要な事業を営んでいた場合、事業を承継する方について新たに申請をしておかなければ事業が停止します。承継する相続人の方が申請手続の代行を希望の場合には、行政書士に依頼することが適切です。
▶四十九日明け ~
ご逝去に関するご連絡をいただいた場合、目安としては1~2か月以内に、ご依頼いただいた相続人様をご訪問いたします。
初回は故人のご生前の生活状況、ご親族関係、相続財産の内容等を伺い、弊事務所がご依頼をお受けした場合のご対応内容やおおよその申告報酬見積額などを提示いたします。
ご依頼の有無については、このお打ち合わせが終わった後でご検討いただき、改めてご連絡をいただければと思います。
その後ご依頼をいただく場合には、まず守秘義務を含む契約書を締結したのち、弊事務所にて被相続人・相続人の皆様に関する情報をお預りします。
伺った相続財産の概要から、相続税や準確定申告の計算に必要な資料について整理し、リストアップしていきますので、相続人の皆様は順次必要資料のお取り寄せをお願いいたします。
なお、金融機関に残高証明書の取寄せ等を依頼すると、相続発生の申し出があったものとして故人の口座での取引が凍結されます。故人の名義で引落とされていた光熱費等を引き続き使用する場合には名義変更手続をお願いいたします。特に故人が事業経営者であった場合や不動産収入があった場合等には、従来その口座で決済されていた未精算の取引がないかよく確認し、必要な場合は取引先に周知してから凍結の手続を取るようお気をつけ下さい。
このほか、故人が遺言書を残している場合、必ず開封せずお申し出ください。公証役場に預けてある場合検索も可能ですので、故人から遺言について伝えられている場合にはその旨お教え願います。
また、相続人の皆様のうちに、消息不明の方・国外に居住されている方・被後見人等である方・相続放棄をご検討中の方などがいらっしゃる場合、このタイミングで情報をいただければ大変助かります。
相続人の中に故人に扶養されていた方がいる場合、遺族年金の受給対象となる可能性があります。年金事務所へ問い合わせをお願いいたします。この方については健康保険等の切替手続が必要となる場合もあります。
この時点で生命保険金の受取手続にも着手できますが、受取った保険金は相続税の納税額が確定するまでは、そのまま預金等としてご保管ください。
▶相続発生後 ~ 3か月
戸籍全部事項証明書(登記簿謄本)や金融機関の残高証明、固定資産税通知書、生命保険の支払通知など、必要な資料が全てお手元に整うまでには通常2~3か月を要します。
遺言書がある場合は、原則この段階で遺産分割が確定しますが、遺言書がない場合は取寄せた資料から財産の全容を把握し、ここから相続人間での遺産分割協議を開始します。
相続放棄・限定承認を希望される相続人様に関しては、相続開始から3か月以内に家庭裁判所への申立て(相続人ご自身または司法書士等から)が必要となりますので、お早めに手続をお願いいたします。
▶相続発生後 ~ 4ヶ月
故人に確定申告すべき所得がある場合、相続開始から4か月以内に準確定申告書(亡くなった方について年度途中で行う確定申告)を税務署に提出します。
準確定申告書は相続人の皆様の連名で提出いたしますので情報のご共有をお願いいたします。
▶相続発生後5~7か月
この時期を目安に遺産分割協議を完了するようご協力ください。
すべての相続人が捺印した遺産分割協議書が作成されると、故人名義の預金の払戻しや不動産の所有権移転登記に進むことができます。
税理士事務所では、遺産分割協議が進んでいる間に、各相続財産の評価を進めます。
相続人の方に不動産等についての現地調査立ち会いや、各種機関へのご同行をお願いする場合もございます。
このほか、予測される納税額がお手元資金のみではまかなえない場合には、相続した資産(不動産・有価証券等)の売却手続等も検討します。
▶相続発生後8~10か月
納税資金確保のための資産売却等についてはこの時期には完了することを目指していただければと思います。
税理士事務所は最終的な分割協議案に基づき各相続人についての相続税額を算出し、相続人の皆様にご報告いたします。
すべての相続人のご了解を得た上で、相続税申告書を被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。
申告を完了した後、申告書控は、相続人代表者の方(ご希望があれば全相続人)宛に納品いたします。
一方、相続人の皆様は、期限までに、申告書記載の相続税額を最寄りの金融機関窓口などから税務署に納付していただく必要があります。
▶相続税の納付後
相続税の納付が完了した段階で、税理士側でお手伝いすることは一旦終了となりますが、相続した財産の受取手続など、相続財産に関してお悩みのことがあれば、随時ご相談ください。
また、故人の事業を承継した相続人の方の相続年以降の事業に関する税務届出・確定申告、相続された資産の売却による譲渡所得申告、相続対策のための贈与などに関するご相談も、別途お受けいたします。