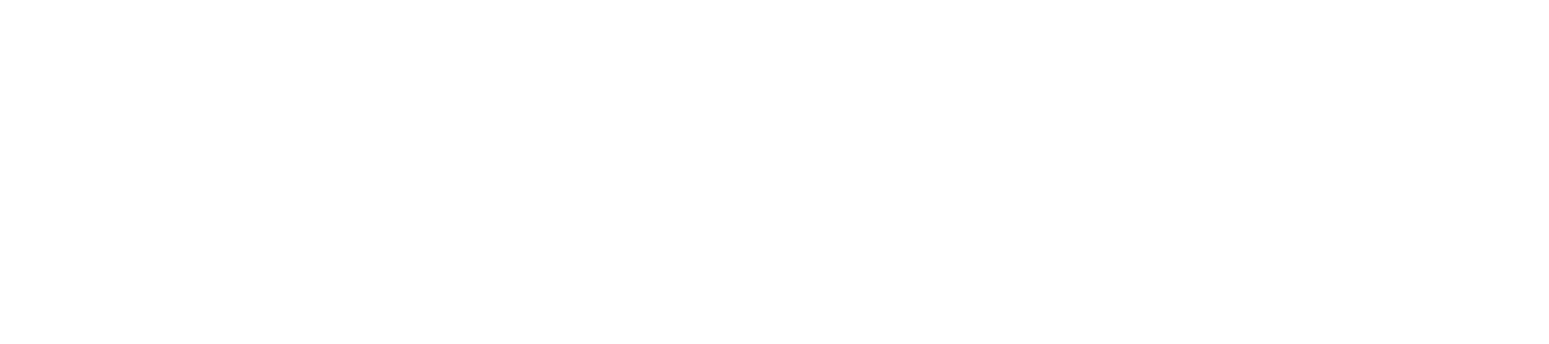- 1.相続に関するご質問
-
料金設定は?
相続財産の評価額の総額・含まれる財産の性質によって異なりますが、ご参考までに料金表をご確認ください。
なお具体的なお見積りに関しては、この価格表をベースに、お客様の状況に合わせた試算をご契約前にご提示いたします。
※申告報酬は相続財産の評価額を基礎に算定いたします。そのため、お見積時に判明していなかった財産が後日発見された場合等には報酬額が変動する場合もございます。相続税は、どうやって申告するのでしょうか?
相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人(故人)の最後の住所地の所轄税務署宛に、すべての相続人が共同して申告書を提出し、納付します。
期限までに相続人間での遺産分割が決まらない場合も、「法定相続分」で分割した場合の相続税額について申告・納付が必要です。また特別な事情がある場合には、特定の相続人が独自の申告書を提出することも認められますが、おすすめはしません。相続が発生しました。いつの段階で税理士に依頼すべきですか?
相続が発生した場合、できるだけ早い段階で一度ご連絡をいただくことをお勧めいたします。
相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内ですが、それよりも前に期限の到来する手続や、事前に関係機関から証明書類を取寄せなければ適用できない優遇税制があります。
着手が遅くなるとその分取れる選択肢が狭まってしまいますので、まずはご状況をお聞かせください。
相続手続の一般的な進め方については、相続ご対応スケジュールのページをご参照ください。相続人同士が遠方なので、なかなか会えないのですが?
遠い親戚の相続等、各相続人の方のご住所も離れていてなかなか集まれない、という状況は多いかと思います。
相続人の皆様のご了承がある場合、相続手続の過程ではリモート・郵送でのご報告によるお打ち合わせにも対応いたします。
但し、最終的な遺産分割協議書へのご署名・相続税申告書のご承認に関しましては、原則として相続人の皆様のご同席の上でのご確認をお願いしております。また、やむを得ずご同席が難しい相続人様に関しては、代表相続人様にも相談しつつ、状況に合わせた方法で必ずご承認をいただいた後に税務申告をいたします。平日は働いています。土日祝日の打ち合わせは可能ですか?
事前のご予約がある場合、弊事務所とのお打ち合わせについては土日祝日でも対応いたします。
但し金融機関・官公庁窓口での問い合わせや手続が必要な場合もありますので、その場合には平日にご対応をお願いすることがあります。申告に必要な元資料は税理士側で取り寄せできませんか?
取得者の権限に制限のない不動産・法人に関する登記事項証明書や、税理士に職務上の請求が許可されている書類(戸籍全部事項証明書・住民票)に関しては取寄せが可能です。但し取得に必要な各種行政手数料・郵送料は、申告報酬と別途、立替実費をご請求いたします。
その他、印鑑証明書・固定資産税の名寄帳・各金融機関の残高証明取得などに関しても、委任状等を利用して代理人からの取得依頼が可能な場合は、ご相談により対応が可能です。但し、これらの手続に関しては、相続人ご本人からの請求の方が手続が圧倒的にスムーズです。お一人での手続きにご不安がある場合は請求手続へお付き添いすることも可能ですので、状況に応じてご対応を検討できればと思います。
また、資産の相続払戻請求に関しては相続人様ご本人でのお手続・相続人様口座への払戻をお願いしております。申告期限が迫っています。依頼できますか?
相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続財産を取りまとめ、評価し、分割方法を決めて、相続税の計算を完了する必要があります。
通常は、これら一連の手順に5~6ヶ月の期間が必要となりますので、ご依頼をいただいた時点で申告期限まで5ヶ月を切っている場合は、少し急がなければならない状況です。打合せの頻度、資料の手配など、通常よりスピードを上げてご対応をお願いする場合があります。
また、場合によっては、申告期限に間に合わず(期限後申告)、追加の税金がかかったり、税額を軽減する特例が使用できない等の影響が出ること、弊事務所側で特別対応の料金を設定させていただくこともございますので、ご了承ください。税務署から突然手紙が届きました。どうしたらいいですか?
お亡くなりになった方についての死亡届が市町村の窓口で受理されると、その情報は税務署に共有されます。税務署側で故人に相当の相続財産があると認識された場合、相続人の方に「相続税についてのお尋ね」という表題の文書を送る場合があります。
この文書が届いたからといって必ず相続税の課税があるとは限りませんが、相続人側で申告が不要と判断した場合も、その旨を記載して返送する必要があります。
どう対応すべきか、不安な場合はご相談ください。改めて状況を確認し、申告不要の場合には単発のご相談対応として、税額が発生する見込であれば相続税申告のご依頼として、状況に応じてご依頼を承ります。準確定申告は、しないといけないですか?
「準」確定申告とは、本来確定申告をするはずだった方が亡くなったため、その相続人が故人に代わってする確定申告を指します。つまり準確定申告の必要性は、故人に確定申告の必要性があったかどうか、ということで判断できます。一般に、故人が事業を行っていた方、不動産収入があった方であれば、毎年確定申告によって所得税(+消費税)の申告・納付をされていたと思われますので、準確定申告が必要と推測されます。
一方、継続的な収入がなかった方についてはそもそも確定申告を行っていない場合が多く、このような場合には準確定申告は不要となります。但し、源泉徴収税額等、生前に納付済の所得税がある場合には、準確定申告の義務がなくても還付を受けるために申告をするという選択肢もあります。この場合の期限は、4ヶ月ではなく5年となります。但し相続財産にはこの還付金を含みますので相続税の申告期限までに手続をお願いします。相続人ですが、財産を相続するつもりはありません。相続放棄の手続を取るべきですか?
「相続財産を受取らない」というだけであれば、強いて「相続放棄」の手続を取る必要はなく、遺産分割協議で相続しない旨を他の相続人と合意すれば足ります。
「相続放棄」は法律上の手続となり、この手続を取った場合、放棄した相続人自身が不利になる場合(生命保険金等)、また他の相続人に影響を及ぼす場合(同順位の相続人が他にいない場合)などがあり、選択は慎重にご判断いただければと思います。遺産分割協議書の作成方法がわかりません。
相続税申告には分割協議書の添付が必要となりますので、相続財産の全容が把握できており、各相続人がどの財産を相続するかが決まっていれば、分割協議書の書式作成に関してはお手伝いいたします。
但し相続財産に不動産が含まれる場合、記載内容が登記申請手続に密接に関わってきますので、分割協議書の作成は司法書士に依頼されるのが適切です。ご要望があれば司法書士のご紹介もいたします。夫が他界しましたが、妻がすべての財産を引き継げば課税されないと聞きました。何もしなくていいでしょうか?
配偶者が相続した財産については、その総額のうち1億6千万円(配偶者の法定相続分の方が多い場合は法定相続分)までは相続税がかからないという制度があります(配偶者の税額軽減)。
この結果、すべての財産を配偶者が相続する場合税額は0円となることも多いです。但しこの制度により納税が不要となるのは、申告期限までに遺産分割協議が確定し、かつ相続税の申告書を提出している場合に限ります。そのため必ず相続税の申告書を作成し・提出する必要があります。
合わせて、特に配偶者以外の相続人が子である場合、二次相続(配偶者から子への相続)の場合の税額を検討する必要があります。今回の相続にかかる財産額、配偶者の方のご年齢や生活状況によりますが、相続財産の一部について、この段階で子が相続し納税した方が、相続人全体の二次相続までを含む納税負担としては有利と考えられる場合があります。この点も含めてご検討いただくことをお勧めいたします。不動産について「小規模宅地の特例」という制度を使えば、税額が発生しないようです。何もしなくていいでしょうか?
上記配偶者の税額軽減と同様、分割協議の確定と申告書の提出が要件となっている制度です。相続税申告書の作成・提出が必要となります。
- 2.贈与に関するご質問
-
料金設定は?
対象の財産・受贈者の人数等によって異なりますが、ご参考までに料金表をご確認ください。
なお具体的なお見積りに関しましては、この価格表をベースに、お客様の状況に合わせた試算をご契約前にご提示いたします。
※相続時精算課税の選択に関しては、選択年以後の贈与については同一の税理士に継続して依頼されることを強くお勧めいたします。
また、選択年以後ご自身または他の税理士に贈与税申告を依頼される場合、過去の届出書・申告書についてはご自身の責任において厳重に管理をお願いいたします。贈与税は、どうやって申告するのでしょうか?
贈与をうけた年の翌年2/1から3/15までに、贈与を受けた人(受贈者)が、受贈者の住所地の所轄税務署宛に申告書を提出し、納付します。
なお贈与税については、国税庁の公表している「確定申告書等作成コーナー」からご自身での申告も可能です。(電子申告の他、出力した申告書を郵送することでも申告できます)申告期限は翌年3月なので、年が明けてから依頼すればよいですか?
贈与のご予定が決まっている場合には、贈与前の段階で一度ご連絡をいただければ幸いです。適用できる制度や、要件などの確認を行います。
また、特に特例の適用などがない場合にも、確定申告期である1月~3月は新規お申込みをお受けできる枠に限りがありますので、年内のご連絡をお勧めいたします。相続税の負担を避けたいです。生前に贈与を受けた方がいいですか?
一般に、贈与税の税率は相続税の税率より高く設定されています。相続は発生時期を制御できないのに対して、贈与は時期や相手、財産の種類を特定して資産を移転できるためです。
そのため、単に税負担の面だけで考えた場合には、贈与した方が有利、とはいえない場合も多いです。贈与の必要性は財産の性質やご家族の事情等も考慮してご検討ください。住宅取得資金を親から贈与された場合贈与税がかからないと聞きました。何もしなくていいでしょうか?
血のつながった両親や祖父母からの住宅取得資金の贈与に関しては非課税とする特例があります。
この制度については贈与のタイミング、受贈者の状況、購入した家屋の性質などに細かい要件があります。また税額が0円の場合にも贈与税申告書と必要な添付資料を期限内に税務署に提出する必要があります。
申告を忘れた場合、また要件に当てはまらない場合には、特例の対象とならず贈与額全額が贈与税の対象となるため、ご注意ください。
- 3.譲渡等に関するご質問
-
料金設定は?
ご依頼の申告内容により異なりますが、ご参考までに料金表をご確認ください。
なお具体的なお見積りに関しましては、この価格表をベースに、お客様の状況に合わせた試算をご契約前にご提示いたします。
※共有不動産の譲渡については、各所有者について申告が必要となりますので、1件あたり料金×共有人数となります。譲渡に関する税金は、どうやって申告するのでしょうか?
個人の方が資産を譲渡したことに関する税金は「所得税」です。
所得税については、毎年1~12月にその故人について発生した所得(事業・不動産・給与・年金・譲渡・配当その他各種)を集計し、その性質ごとの税率を適用した税額について、翌年3/15までに、住所地の所轄税務署宛に申告書を提出し納付します。
そのため、申告のご依頼をいただいた場合には、その年の譲渡以外の所得に関する情報についてもお伺いし、資料をご提供いただくこととなりますのでご了承ください。
なお譲渡所得税を含む所得税申告については、国税庁の公表している「確定申告書等作成コーナー」からご自身での申告も可能です。(電子申告の他、出力した申告書を郵送することでも申告できます)申告期限は翌年3月なので、年が明けてから依頼すればよいですか?
譲渡のご予定が決まっている場合には、売却前に一度ご連絡をいただければ幸いです。適用できる制度や、要件などの確認を行います。
また、特に特例の適用などがない場合にも、確定申告期である1月~3月は新規お申込みをお受けできる枠に限りがありますので、年内のご連絡をお勧めいたします。税務署から突然手紙が届きました。どうしたらいいですか?
不動産を売却した場合、登記名義が変わるため、法務局から税務署に情報が共有されます。その不動産の売却について譲渡所得(売ったことによる利益)の申告がない場合には税務署が「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という表題の文書を送る場合があります。
譲渡所得がない場合等には譲渡所得の申告は不要であり、この文書が届いたからといって必ず課税があるとは限りませんが、申告不要と判断した場合も、その旨を記載して返送する必要があります。
どう対応すべきか、不安な場合はご相談ください。改めて状況を確認し、申告不要の場合には単発のご相談対応として、税額が発生する見込であれば確定申告のご依頼として、状況に応じてご依頼を承ります。相続・贈与で受け継いだ資産を売却しました。譲渡所得はどうやって計算しますか?
譲渡所得は、「収入金額▲取得費▲譲渡費用」で計算されます。相続・贈与で受け継いできた資産の場合、この「取得費」はそもそもの持ち主(被相続人や贈与者)がこの資産を取得したときの価額です。相続税申告・贈与税申告の際の財産評価額等は使用しません。また、保有期間も相続・贈与のあった時期ではなく、当初の取得日から譲渡日までの期間を採用します。
ただこのような場合、そもそもの取得時期が古すぎて、当初取得時の領収書等が残っていない場合があります。こういった資産については、取得費として「収入金額×5%」を採用してよいことになっているため(概算取得費)、譲渡所得の計算にあたっては原則としてはこの方法を使用します。但し正式な領収書等が発見できない場合でも、購入時の資料の中から何かしら実際の取得費の手がかりを得られる場合もありますので、もし資料がある場合にはご相談の際ぜひお持ちください。
- 4.弊事務所のサービス内容に関して
-
はざま税理士事務所の特徴は?
税理士ひとりの小さな事務所です。ご対応については、すべて私が行います。
相続専門を謳う大手事務所のように、名だたる資産家の相続案件をいくつも請け負うような華やかな仕事はしていません。
ただ、だからこそ、ひとつひとつの案件に真摯に向き合えればと考えています。相続は、故人と相続人の皆様の人生が見えるお仕事と感じています。
私自身も何度か親族を見送り、そのたび目の回るような思いをしました。すべてのご負担を肩代わりすることはできませんが、少しでもお手伝いすることができればと考えています。申告依頼と単発・個別相談の違いは?
相続税・贈与税・譲渡所得税について、税額計算および税務申告を行う場合、申告のご依頼として承ります。この場合申告料金にご相談料金も含みます。
一方、税務申告を伴わず、ご相談のみの場合には単発・個別相談として時間単位でご相談に対応いたします。ご相談料は基本的には実際にご面談に要した時間でご請求いたしますが、そのご相談に関して事前に試算や調査を行う必要があった場合、準備期間や資料の取寄せに要した時間数を加算させていただく場合がございます。この場合、必ずお客様に見積書を提示し、ご請求金額についてご了承をいただいたのちご請求いたします。
_ 相続等ご対応スケジュール
_ 相続等に関する料金表
_ 事務所案内
_ はざまについて
_ BLOG
_ お問い合わせ