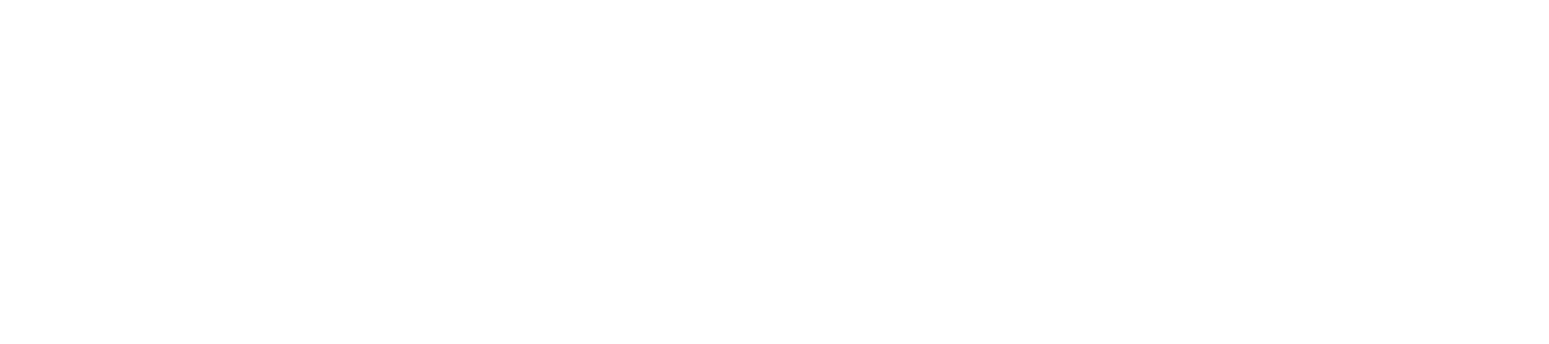- 1.税理士への依頼がはじめての方へ
-
税理士って何する人ですか?
税理士はまずは税金の専門家であり、各種の税金に関する申告代理・相談対応を行うのが本来の仕事です。
ただ、多くの税理士が関与しているのは管理部門の体制が手薄な小規模の事業者であることもあり、実際の業務範囲は上記にとどまらず、税額計算の基礎である会計業務、事業資金の調達支援、税務会計上のリスク対策、事務処理効率化など、経営とお金に関する総合的なご支援も含まれます。また事業の成長段階に合わせて、経営者に他分野の専門家や支援機関など適切なご相談相手をご紹介し、事業の体制を整えていくことも業務の一環となっています。
一言でまとめるのが難しいですが、私としては「経営者の最初の相談相手」でありたいと考えています。
また、上記の中でも私が得意なのは「事業やお金に関する雑多な情報を整理し、経営者の視界をクリアにすること」ではないかと考えています。税務署と税理士の違いは何ですか?
税務署は、国の税金を管轄する役所であり、広く国民全体に向かって税金に関する様々な対応を行っています。
一方、税理士は民間の事業者であり、特定の依頼者との契約に基づきサービスをご提供しています。
確定申告時期、税務署でも税務相談や申告補助を行っていますが、これはあくまでも無償の公共サービスの範疇であり、個別の事情にはあまり配慮せず短時間で簡易的な対応に留まります。
一方、税理士は有償の事業としてご依頼をお引受けするため、会計全般に関するより広範で柔軟なご対応が可能です。もちろん国以外の県や市の税金に関する対応も行います。税理士と会計士の違いはなんですか?
税理士資格取得にはいくつかのルートがあり、そのうちのひとつが、公認会計士資格の取得です。公認会計士は通常、監査法人に所属し上場企業の監査(一般投資家に公開する財務情報の確認)を行うことを主な業務としています。しかし監査法人を退職した場合には、企業会計の専門家としての知識と経験を生かし、税理士登録も行って税理士業務に参入することが多いです。
公認会計士資格を有していても、税理士としての実際の業務内容は他の税理士と大きく変わるところはありません。ただ、上場企業の会計に関わっていた経験などから、大規模法人への対応や、IPO・M&Aなどの知識が他の税理士より豊富な場合が多いです。一方で、家族経営の小規模企業での相続等も関わるような税務対応に関しては、税理士の方が実務経験が豊富な場合が多いです。とはいえ、これはあくまでも傾向の話です。税理士事務所と会計事務所の違いはなんですか?
一般に、公認会計士資格も有する税理士の場合「会計事務所」という呼称を選ぶことが若干多いような印象はありますが、この呼称には特に制限があるものではなく、公認会計士資格を有しない税理士の事務所でも「会計事務所」という呼称を使っている場合もあります。つまり、「特に違いはありません」。
税理士法人って何ですか?
「税理士法人」は、税理士が法人成りした場合の名称です。「税理士法人」としての登記をするためには、税理士資格のある社員が2人以上必要という制限があります。そのため「税理士法人」には、複数の税理士が在籍していると考えていただければよいです。
但し個人の「税理士事務所」であっても複数の税理士を雇用している場合や、「税理士法人」であっても実際にはその拠点に配置されている税理士は1人という場合もあり、これだけで実質的な体制が判断できるわけではありません。税理士と顧問契約するメリット・デメリットは何ですか?
▶メリット
事業についての総合的・継続的な支援を受けられます。これは、日々の会計入力や毎年の申告の手間を減らせるという意味だけではありません。
顧問税理士は継続的に経営者の方のお話を伺い、事業内容について理解しているため、日々の取引の中で発生する問題に対し、事業の特性や経営者の性格を考慮した上での適切な解決策を示したり、潜在的なリスクに関する警告、適時の節税提案などをご提供することができます。いわばあなたの事業に合わせたオーダーメイドのサービスです。
▶デメリット
税理士はあくまでも親族や従業員等ではなく、外部の事業者です。情報の共有やご意向の理解、意思疎通などに関して最初から阿吽とはいかない部分もありますので、その点はご協力をお願いいたします。
また税理士は税金や会計の専門家であり、経営についての専門家ではありません。各事業の専門分野についても、経営者以上の知識を持っているわけではありません。
税理士と契約して売上が増えるわけではありません。経営者の味方でありたいと考えていますが、状況によっては事業を守るため第三者の立場としてご意向に沿わない諫言をする場合もあります。
この点をご理解の上ご用命ください。顧問契約と単発・個別相談の違いは?
弊事務所では、事業に関するご相談について、年単位での顧問契約と、時間単位での単発・個別相談のメニューをご用意しております。
顧問契約の場合
継続的に事業のご状況を拝見し、また会計帳簿や申告書作成を通して事業内容やご意向について理解した上でサービスをご提供します。そのため、よりお客様のご希望に添ったご提案が可能です。
単発・個別相談の場合
特定のご相談案件について、その都度ご提供いただいた資料・情報の範囲内でご回答いたします。そのため、事前に必要な情報についてご共有をお願いいたします。
※単発・個別相談についてはご相談用のメニューとなっております。会計帳簿の作成や申告は基本的にお受けしておりません。
※確定申告時期など顧問業務繁忙期には、顧問契約のお客様へのご対応を優先いたします。単発・個別相談のご依頼に関し日程調整等をお願いする場合がございます。
※単発・個別相談のご要望であっても、内容・頻度によっては顧問契約の締結をお願いする場合もございます。税理士事務所ごとにずいぶん料金に差があるようです。相場はどのくらいですか?
「税理士って何する人ですか?」でご説明したとおり、税理士の業務は広範に渡ります。このため月額顧問料に含むサービス・別料金としているサービスも事務所ごとに異なり、単純比較が難しいのが実情です。
かつては法律で定められた報酬規定がありましたが、25年前に廃止となりました。(個人事業2万/月~、法人3万/月~)。10年ほど前まではこの規程を参考にしている事務所も多かったので、これが「相場」といえるかもしれません。
ただ、昨今の物価高騰もあり、現在はサービス提供内容に応じて独自の料金を設定している事務所が多くなっています。この中には非常に安い月額顧問料を提示して集客する戦略の事務所もありますが、実際には必須のサービスなどが別料金設定とされていて、結局それほど価格に差が出ないというような場合も多いです。
弊事務所では、「わかりやすい価格設定が信頼性につながる」「追加費用を理由に非効率な選択をしていただきたくない」という考え方に基づき料金表を作成しています。自明のことですが、極端に安い価格のサービスは長く品質を保てません。そのため弊事務所では理由のない値引き等は行っておりません。ご了承ください。はざま税理士事務所の特徴は?
税理士1人の小さな事務所です。そのためご依頼の検討にあたっては、経営者の方ご自身が私とお話いただいて、方針や考え方が近いと感じられるかどうかが一番重要と考えております。
事業のご支援にあたっては、ご支援の基本方針でお伝えしているとおり、資金の流れを重視し、長期的視野に立った健全な事業継続を支えたいと考えています。
私自身がこじんまりした事務所を経営しているからこそ、お客様と共に「小さくても強い、自分の個性を生かした事業」のよさを証明していけるのではと思っています。
経歴や自己紹介について、詳しくはははざまについてをご参照いただければと思いますが、高齢の男性の多い税理士の中では、わりと話しかけやすい存在感だと思っています。
「意外と色々知ってるベテラン経理さん」くらいの距離感で事業に寄り添えたらと考えています。肩の力を抜いてご相談にいらっしゃってください。
- 2.弊事務所のサービス内容に関して
-
料金設定は?
法人・個人の別、売上規模、サービス内容によって異なります。ご参考までに料金表をご確認ください。
なお具体的なお見積りに関しましては、この価格表をベースとして、お客様のご状況に合わせた試算をご契約前にご提示し、ご了承いただいた上でご契約にすすみます。
※料金表の「年間売上高」欄に関しては、前期の実績がある場合にはこれを使用し、創業の場合には創業計画の当期売上見込額を使用いたします。営業日はいつですか?土日祝日の対応は可能ですか?
原則として月~金曜日 10:00~18:00が営業時間、土日祝日はお休みとなっていますが、事前のご予約により土日祝日のご対応も可能な場合があります。ご相談ください。
創業準備中です。創業(法人設立)してから相談に行った方がいいですか?
ぜひ、創業される「前」にご相談いただきたいです。開業から一定期間を経過すると適用できなくなる措置等もあるため、開業予定が決まりましたらお早めにお問合せをいただければと思います。
融資を受けたい。どの段階で相談に行くべきですか?
融資をご検討中の場合も、金融機関へ連絡する「前」にご相談をいただければと思います。
融資は受けることがゴールではなく、返済をすべて完了するまででゴールです。無理のない計画を立てられているか、ご一緒に検証してから申込みをお勧めいたします。
また、金融機関のご紹介、面談への同行、事業計画作成等もご要望に応じてお手伝いいたしますのでお申し付けください。創業時から税理士に依頼した方がいいですか?
創業当初は取引も少ないし、また落ち着いたら依頼を検討しよう、と考える経営者の方が多いですが、このタイミングでバックオフィスの仕組みを整えておくと、本格稼働後が非常にやりやすくなります。
またこの時期の選択が、数年後に大きな影響を及ぼすこともあります。経営上のご不明点はそのままにせず、早めに対処していくことをおすすめいたします。
何かと目が回るほど忙しい時期、弊事務所で支援できる部分はお任せいただければと思います。創業期のお客様の場合、売上等のご状況によっては料金のご相談にも応じますので、まずはご連絡ください。小規模な不動産経営です。顧問契約が必要ですか?
賃貸物件数が4棟(室)以下で、期中取引内容に大きな変動がない場合には、弊事務所の判断で特別価格でのご対応をご提案できる場合もございます。
但し関与の初年度については複数回のお打ち合わせが必要となります。また、物件の修繕・売却等状況に変化があった場合には改めて価格の見積をご提示いたしますのでご了承ください。簡単な相談なので、無料で対応してくれませんか?
顧問契約ご検討中のお客様に対する初回面談は無料となっております。但しこの面談では、基本的に個別具体的な会計・税務に関するご相談にご回答を差し上げることは難しい点ご了承ください。
具体的な事例に関する無料での相談対応に関しましては、私も所属している東京地方税理士会甲府支部主催の無料相談会等で対応しておりますので、ご利用をご検討ください。
また、弊事務所では単発・個別相談メニューのご用意もございます。有償でのご相談対応に関してはこちらをご利用ください。記帳(会計帳簿への入力)はしてくれますか?
はい、お引き受けします。
経営者の方にとって、帳簿は経営判断のための「素材」であって、事務作業に多大な時間を要したり、帳簿作成が「目的」になっては意味がないからです。
但し、信頼に足る最新の「素材」をお届けするためには、タイムリーな資料のご提供・お問い合わせへのご回答など、経営者の方から会計事務所へのご協力が不可欠であることをご理解ください。
また、目安として年間売上高5,000万超のお客様に関しては、社内の管理体制を整えていく必要から経理担当者の採用と自社での会計入力をお願いする場合がございます。記帳を依頼する場合、しない場合で価格は変わりますか?
価格は変わりません。
記帳を弊事務所でお引受けする場合も、お客様がご自分で入力される場合(自計化)も、弊事務所にはそれぞれに必要な対応があり、自計化=弊事務所の省力化とはなるわけではないためです。
弊事務所から自計化を推奨するのは、工事業等現場でしか把握できない情報がある場合、また事業規模拡大に伴い社内での経理体制整備が適切な状況となった場合です。
もちろん、経営者の方のお考えとして、早い段階から自社内で経理人材を育成をしたい等のご意向があれば、お申出により自計化のご依頼をお受けします。数字は苦手、全部お任せでやってほしいのですが?
会計帳簿・税務申告書の作成はお引き受けいたしますが、その作成にあたっては経営者の方のご協力が不可欠です。
例えば、今後どのような事業展開を目指していらっしゃるのか、そのために必要な資金はどのくらいなのか、といった将来の見通しによって、税制上の選択が大きく変わる場合があります。
また、過去の売上・仕入・経費に関しても、現場を把握している方からの情報がなければ、税理士の想像で勝手な判断をすることはできません。
適切な時期に必要な情報のご提供がなかった場合、税理士としてはリスク回避のため保守的な選択をせざるを得ない場合、適切な節税を選択できない場合もあります。
事業を守り、経営者の方に不利益を与えないという観点から「丸投げ」のご希望にはお応えできません。面談って、何をするんですか?
関与の初期段階にあっては、事業内容や経営方針の理解、会計ソフト等設定作業、業務フローの整備が主な目的となります。
運用が安定してきた後は、今後の事業展開や投資計画について経営者の方のご意向を伺ったり、弊事務所からの情報提供を行う時間としています。
お話を伺う中で予算に織り込んでいない新たな計画が判明した場合などには、概要を把握し次月以降の計画に反映いたします。
弊事務所からの情報提供に関しては、毎月の報告資料に関する補足説明、活用できそうな制度や関連のある法改正のご案内等が主な話題となります。
このほか、日常的なご質問については原則として日々チャットでご対応しておりますが、チャットでは書ききれないようなご質問へのご回答や、税務上複数の選択肢がある場合の解説などもこの機会に行います。
決算時期は決算報告・予算策定、融資ご検討の場合には金融機関に提出する事業計画なども検討する必要があり、毎回話題は多いです。
疑問点はこの機会に解消してスッキリ仕事に戻っていただきたいと考えているため、面談時間には制限を設けていません(1.5h~3時間程度の方が多いです)事務処理は従業員に任せているので、そちらと直接やり取りしてほしいのですが?
経営者の方・弊事務所・従業員様をメンバーとするグループチャットの作成にご協力ください。
その上で、会計資料のご提出等事務的なご対応については、そのチャット経由で従業員様にご連絡いたします。
但し、ご面談の際には経営判断に関わる話題も多いため、必ず経営者様ご自身にご同席ををお願いできればと考えております。
また、チャットでの事務処理対応に関しても、従業員様で判断がつかない点は、随時経営者の方にご対応をいただきますようご協力をお願いいたします。事業が忙しいので、経理資料は3ヶ月に1回程度まとめて渡せませんか?
日常的に売上が上がっている状況の場合、原則として毎月の資料提出をお願いしております。
但し創業直後で売上がまだない場合、また賃貸物件数4棟(室)以下の不動産所得の場合は、一度ご相談ください。税理士変更を検討中です。前の税理士と直接やりとりしてくれませんか?
原則として前任の税理士に対する私からのご連絡は控えております。
恐れ入りますが、お客様ご自身にて必要な資料の入手をお願いいたします。
ご参考までに必要資料をリスト化してお渡しいたしますのでご活用ください。
なお、税務署提出済資料に関しては、前任の税理士から入手ができない場合もeTaxまたは税務署窓口にて閲覧が可能です。PC操作やメールは苦手です。連絡は基本的に電話で話したい、資料は回収に来てほしい。
ひとりで対応している事務所のため、私自身の時間的な制約が多く、現実的にご希望に添うご対応が難しいです。
より適性の合う他の事務所をご検討いただければと思います。契約後、解約したいときはどうしたらいいですか?
顧問契約中の場合でも、お客様からの解約の申出があった時点で、ご契約を解消することが可能です。
ただしその時点までに未払の顧問料が発生している場合には、お支払が完了次第のご解約となります。
共有フォルダ内の会計データについてはお手元へダウンロードをお願いいたします。
会計ソフトは、料金を払ってある期間内は継続してご利用いただけますのでご安心ください。会社の設立登記、取引の契約書のチェックや、社会保険手続も全般お願いしたいんですが?
税理士の業務範囲を超える業務に関しては提携の他士業をご紹介いたします。
各士業の業務範囲としては、登記は土地家屋調査士または司法書士、契約書のチェックは弁護士、社会保険手続書類の作成は社会保険労務士、許認可申請等公的書類の作成に関しては行政書士、などとなります。
但し、誰に依頼したらいいか分からない、該当の士業の知り合いがいない、などの場合には、ご遠慮なく、まずは弊事務所までご相談ください。毎月資金繰りに追われています。契約したら状況は改善しますか?
はっきりと認識できるほど資金繰りが悪化している場合、よほど事業が好転しない限り、事態は一朝一夕で打開できません。
応急措置として融資を受けることができる場合もありますが、特別な事情でなく日常的に資金が枯渇しているのであればその融資も長くはもちません。
根本的な体質改善をしなければならない状況です。
このような状況に至っている場合、私と契約をしていただいても、打ち出の小槌をお出しすることはできません。
私にできるのは、現状の情報整理と問題点の洗出しです。事業について決断し、行動し、体質を改善できるのは、経営者自身だけです。
私以外の税理士に依頼したとしても、その点は同様です。
資金繰りが枯渇する状況が継続している場合、原因は主に3つ、
・売上がそもそも少ない
・粗利に比べて経費が過大
・事業主等が利益以上に費消している
それぞれについてご一緒に検討を行い、具体的な改善策を考えることになります。
時には事業が急速に発展中で、既存事業の利益だけでは追いついていない場合もあります。しかし、そもそも既存の事業の屋台骨が砕けている場合もあります。いずれにしろ、一度立ち止まる必要があります。
早期に正確な状況整理が必要な状況ですので、必要な経理資料の適時のご提出、お問合せへの早期のご回答、ご自身での継続的な現金出納帳や日次の資金繰表作成等のご協力がなければご対応は難しい点、ご了承ください。
なお、ご状況によってはご依頼をお受けできない場合、事業継続でなく事業の整理・廃業をおすすめする場合もございます。将来のことなんてわかりません。予算って必要ですか?
上場企業とは異なり、小規模事業の場合、予算はあくまでも経営者の目線合わせの材料です。
予算は基本的には前年実績を参考に、経営者の方の目論見や今年の変動予定を織り込んで作成しますが、もちろん、実際は予算どおりには進みません。
でも過去の実績だけをいくら眺めても、未来はぼんやりとしか見えません。実績と、今後の見通し(予算)を実際の数字で組み合わせることで、「期末の着地は」「その着地の場合の税額は」「その予定で、資金は残るのか」を、あくまでも仮ではありますが、明確な数字で把握することができます。
だからこの予算は、後で答え合わせをしたり差額を追求するためではなく「今の予定で進んだら大体どうなるのか」を数字で表すための道具として使っています。
「今の予定で進んだら、資金が回るはず」の場合、一時的な想定外があっても資金調達できる可能性は高いですし、予定の組み直しもしやすいです。
ただいつの間にか、「今の予定で進んだら、資金が残るわけがない」構造になってるのかもしれません。それなら、問題は一時的ではなく致命的です。
予算の情報は、その確認をするために継続的に収集をしています。